1.事業承継税制の拡充
中小企業の経営者の高齢化が急速に進展する中で、集中的な代替わりを促すため、10年間の特例措置として、事業承継税制が抜本的に拡充されました。
※平成30年1月1日から令和9年12月31日までの相続または贈与について適用されます(令和5年3月31 日までの間に特例承継計画を都道府県に提出した場合に限ります)。
(1)入口の要件の抜本緩和
◆対象株式数上限等の撤廃
現行制度では、先代経営者から相続または贈与により取得した非上場株式等のうち、議決権株式総数の2/3に達する部分までの株式等が対象(相続または贈与前から後継者が既に保有していた部分は対象外)とされています。したがって、例えば相続税の場合、猶予割合は80%ですので、猶予されるのは2/3×80%=約53%のみに留まっていました。
今回の改正により、対象株式数の上限が撤廃され(現行:2/3→改正後:3/3 )、かつ、猶予割合が100%に拡大されるため、事業承継時の相続税・贈与税の現金負担はゼロになるのです。
◆承継パターンの拡大
現行制度では、一人の先代経営者から一人の後継者へ相続または贈与される場合のみが対象でしたが、親族外を含む複数の株主から、代表者である後継者(最大3人)への承継も対象になりました。
(2)税制適用後のリスクを軽減
◆承継後の負担の抜本軽減
現行制度では、後継者が自主廃業や売却を行う際、経営環境の変化により株価が下落した場合でも、承継時の株価を基に相続税・贈与税を納税しないといけないため、過大な税負担が生じるという可能性がありました。
今回の改正により、会社を譲渡(M&A)・解散した場合には、売却額や廃業時の評価額を基に納税額を再計算し、事業承継時の株価を基に計算された納税額との差額が減免されることとなります。
◆雇用要件の抜本的見直し
現行制度では、事業承継後5年間平均で、雇用の8割を維持することが求められています。ですので、もし仮に雇用8割を維持出来なかった場合には、猶予された相続税または贈与税の全額を納付しなくてはならないのです。
このことが制度の利用を躊躇する要因となっていたため、雇用要件を実質的に撤廃することにより、雇用維持要件を満たせなかった場合でも納税猶予を継続することが可能になりました。ただし、5年間で平均8割以上の雇用要件を達成できず、かつ、経営が悪化等している場合には、認定支援機関の指導助言が必要となります。
(3)相続時精算課税制度の適用範囲の拡大
現行制度では、相続時精算課税制度(※)は、原則として直系卑属への贈与のみが対象とされています。
今回の改正により、現行制度に加えて、事業承継税制の適用を受ける場合には、60歳以上の贈与者から、20歳以上の後継者(贈与者の子や孫でない場合でも適用可能)への贈与が相続時精算課税制度の対象に追加されます。
(※)相続時精算課税制度とは
「相続時精算課税制度」は、60歳以上の父母または祖父母から20歳以上の子・孫への生前贈与について、子・孫の選択により利用できる制度です。財産の贈与を受けた時には、その財産に対する軽減された贈与税を支払い、その後、父母又は祖父母に相続が発生した時に、その贈与財産とその他の相続財産を合計した価額を基に計算した相続税額から、既に支払った贈与税額を精算します。
この制度には2,500万円の特別控除があり、同一の父母または祖父母からの贈与においては2,500万円に達するまで何回でも控除することができ、その限度額までの贈与には贈与税がかからないことになります(ただし、相続時精算課税制度を利用した場合、贈与税の基礎控除(110万円)の利用はできません)。
贈与額が2,500万円を超えた場合には、超えた額に対して一律20%の贈与税が課税されますが、その贈与税は相続時に相続税額から差し引かれ、相続税額が少ない場合は差額が還付されます。相続時精算課税制度は、選択制ですから、例えば父からの贈与については選択するが、母からの贈与には選択しない(従来の贈与を適用する)ことができます。ただし、一度選択したら取り消すことはできませんので注意が必要です。
<参考>事業承継税制の適用を受けるための手続き
事業承継税制の適用を受けるためには、「都道府県知事の認定」、「税務署への申告」の手続きが必要となります。
①贈与税の納税猶予についての手続き
・提出先は「主たる事務所の所在地を管轄する都道府県庁」です。
・平成30年1月1日以降の贈与について適用することができます。
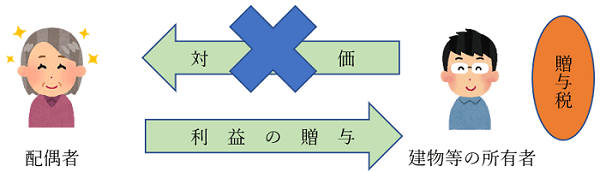
②相続税の納税猶予についての手続き
・提出先は「主たる事務所の所在地を管轄する都道府県庁」です。
・平成30年1月1日以降の相続について適用することができます。
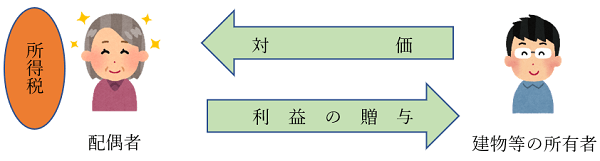
2.小規模宅地の特例の見直し
(1)居住用宅地等の小規模宅地の特例
居住用宅地等の小規模宅地の特例とは、一定の要件を満たす被相続人等が居住していた家屋の敷地について、330㎡までの面積について土地全体の相続税評価額が80%減額されるという規定であり、その分相続税の負担が大幅に軽減されます。
その土地を相続する被相続人の親族のうち、下記の要件を満たす方についてこの特例を適用する場合、いわゆる「家なき子特例」と言われます。
①居住制限納税義務者又は非居住制限納税義務者のうち日本国籍を有しない者ではないこと。
②被相続人に配偶者がいないこと。
③相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた被相続人の相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合の相続人)がいないこと。
④相続開始前3年以内に日本国内にある取得者又は取得者の配偶者が所有する家屋(相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋を除きます。)に居住したことがないこと。
⑤その宅地等を相続開始時から相続税の申告期限まで有していること
今回の改正では以下の2つの変更があり、居住用宅地等について小規模宅地の特例の適用が厳しくなりました。
まず1つ目が、上記④における「相続開始前3年以内の所有家屋」の判定です。相続開始前3年以内に「取得者又は取得者の配偶者が所有する家屋」に加えて「3親等以内の親族、またはその者と特別な関係のある会社が所有する家屋」が追加され、孫や被相続人、関係会社などの持ち家に住んでいる者も特例の適用除外となりました。
2つ目は、相続開始時点で相続人が住んでいる家の過去の所有状況要件が追加されました。具体的には、相続開始時点で相続人が住んでいる家を、過去に相続人自身が所有していたことがある場合、特例が受けられなくなりました。
(2)貸付事業用宅地等の小規模宅地の特例
今回の改正により、相続開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供された宅地については、小規模宅地等の特例の対象から除外されることとなりました。
この規定は2018年4月1日以後に相続等があった場合に適用されますが、2018年3月31日以前から貸付事業の用に供されている宅地等については、小規模宅地等の特例の適用が可能です。
また、相続開始前3年以内に貸付事業の用に供した宅地等であっても、相続開始の日まで3年を超えて事業的規模(準事業以外)で貸付事業を行っている者が貸付事業の用に供している宅地は、小規模宅地等の特例の適用対象となります。
<参考>小規模宅地等の特例とは
「小規模宅地等の特例」とは、被相続人が住んでいた自宅の敷地や事業を行っていた土地について、一定の要件を満たす必要はありますが、その評価額の80%または50%が減額される特例のことを言います。
その中でも「居住用宅地等」とは、被相続人の居住の用に供されていた宅地等であり、被相続人の親族が相続又は遺贈により取得したものをいいます(申告期限までの事業継続、保有継続など、一定の要件を満たす必要があります)。
また、「貸付事業用宅地等」とは、被相続人等の貸付事業の用に供されていた宅地等であり、被相続人の親族が相続または遺贈により取得したものをいいます(居住用宅地等と同様、一定の要件を満たす必要があります)。
居住用宅地等に該当する場合は330㎡を限度に評価額が80%、貸付事業用宅地に該当する場合は200㎡を限度に評価額が50%減額されるというもので、非常に大きな節税効果があります。
3.一般社団法人等に関する相続税・贈与税の見直し
同族関係者が理事の過半を占めている一般社団法人・一般財団法人について、その同族理事の1人が死亡した場合、当該法人の財産のうち一定金額を対象に、当該法人に相続税が課税されます。
この規定は、平成30年4月1日以後の相続について適用されます。ただし、同日前に設立された一般社団法人等については、令和3年4月1日以後の当該一般社団法人等の役員の死亡に係る相続税について適用されます。
4.外国人の出国後の相続税等の納税義務の見直し
高度外国人材等の受入れと長期滞在を更に促進する観点から、外国人が出国後に行った相続・贈与については、原則として国外財産には相続税等が課税されないこととなります。
ただし、出国から2年以内に再び日本に住所を移した場合には、出国後に行った国外財産の贈与に贈与税が課税されます。
この規定は、平成30年4月1日以後の相続または贈与について適用されます。